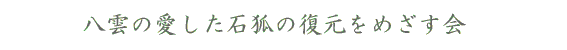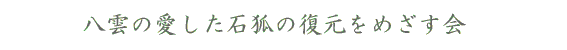|
例えば寛永15年の「萬御定」御供米の条に大社、日御碕に次いで3番目に当社が載っているし、延享5年執政が「稲荷八幡両社の儀は余社と違い、御城内に於いて御自分御勧請之社なるによって・・・・」と表現しているように、格別の社格で明治維新に至るまで別当、神主、二の神主(時には鼕取)を配し、平田新田にて社領を定め、祭祀、造営等すべて藩費をもって弁じ、江戸参覲の首途及帰着には先ず当社に参詣し、次いで他社にも奉告したとある。従って現在の本殿は文化9年の造営であるが、欅造内外の彫刻は名作で近在まれな名建築である。代々藩主寄進の宝物も多く存し、中でも初代直政公の甲冑、萬冶2年銘入面箱、能面、2代綱隆公筆巻物、6代宗衍公大字額、7代不昧公筆額、巻物、名工如泥作神狐其の他、蒔絵大額が有名である。
かくしてその霊験は古来おびただしく伝えられ、城内といえども参拝者の出入は自由であったから地方の人々もこぞって信仰し、人心安定と殖産興業の神として深く人々の心の拠りどころとなり、当社の広大な御神徳は藩内一円に深く浸透し、平和な繁栄の中に、人々みな神を敬い、人情美しく、誠実勤勉の気風を養って今日に及んだ。かの12年目毎に行われるホーランエンヤは日本三大船神事の一つといわれる大盛儀であるのも御神徳を物語るものである。

また、小泉八雲(ラフカディオ・ヘルン)は当社と堀一つ隔てた所に住んでいたが、よほど気に入ったと見えて、彼の著書にしばしば登場する。その一つ、石狐は今はずいぶん数が減ったがそれでも大小数百は現存し観光客にも珍しがられている。彼が最もほめていたという出来の良い石狐(高さ台共5尺)は過年東京池袋で開催された八雲展に出張した。当社の神札は火難除としても市中どこの家の軒先にも貼られていたので彼は当時の松江の唯一の防火設備だと紹介し、その神札を大英博物館に送っているのも面白い。
|